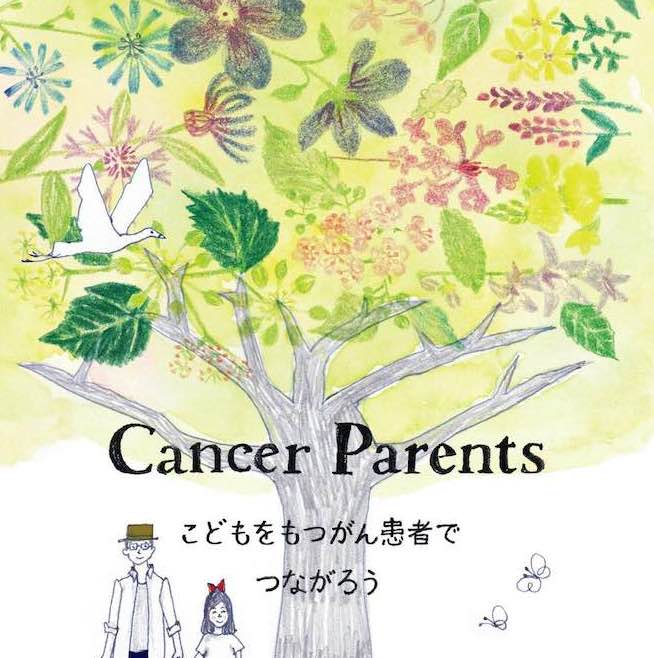2025-08-18 12:36:47
生死観の変化
日記
変化というか、これまで全く考えてなかっただけなのですが、改めて自分ごとになると考察が冴え渡る気がします。
未熟も未熟ですが、自省録としてここに書き記したいと思います。
(以下の文、一般的な趣旨とは逸脱した内容かもしれずご容赦ください。自分を含めたがん患者の立場を軽んじているかのような論調に見受けられる可能性を排除できませんが、自分なりの独特ながらも前向きな立ち合い方であるとお含み置き願います)
5年生存率が約50/50とのことから、まるでシュレディンガーの猫(量子の重ね合わせにより、生と死とが同居する状態)のような宙ぶらりんの状態になってしまい、本当にどちら側にも偏重しないメンタリティが養われていて、これはこれで哲学大好きな自分にとってはある意味で神様が与えてくれた唯一無二の機会とすら感じたりもします。
どちらに転ぶのか本当に分からない為に、どちらにも主眼を置かずにただ見る、2つの事象を同じだけの敬意と畏怖を込めてただ観察することを心掛けています。
即ち、今までは当たり前のように生きることを基準に思考を巡らしていましたが、半分は死の側面から物事を捉える領域に畏れ多くも足を踏み入れてみたいと思います。
この試みは、未知の恐怖に知性で打ち克つ挑戦であり、未知の興奮に洞察で応えるかけがえのない夏であり、童心のように忘れられない冒険でもあります。
僕は中学高校と仏教学校にいたこともあり、死は輪廻転生のスタート地点という考え方がベースにあります。自然科学的にそうだと信じているわけではなく、人生を生きやすくする為に実装したポリシーという感じです。
一方、同じ仏教でも一部では無常感的生死感が存在し、すなわち平家物語の冒頭のように祇園精舎の鐘の声に諸行無常の響きを覚えるわけです。(ただこれはこれで、この冒頭の書き出しは仏教観にそぐわないという反論もあるようですが、ここでは一旦置いておきます)
前者のように新たな旅路につく説と、後者のように終われば無に帰す唯物論は、日本だけでなく世界中の至る所の文化圏でそれぞれ確認されます。
たとえばインドのヒンドゥー教では、これは仏教の元祖なので納得感もあるのですが、やはり輪廻転生の考えが強いです。3年間インドに駐在したことがありますが、確かに現地人は日本人に近い生死観があります。
輪廻転生しつつも、一方では先祖のいる世界(あの世)で久方の再会を果たせるという、なんか都合よく1人が2人に増えてないかとツッコミを入れたくなる思想も日本とほぼ同じで、お盆の正式名称の盂蘭盆はもともとはサンスクリット語のウランバナーという行為を指すところから来ているようです(それぞれの持つ意味合いは少し異なるようですが、最終的には供養という意味です)。
ちなみになぜ輪廻転生しつつあの世で先祖と暮らせるのかという問題(まるで冒頭の量子重ね合わせがここでも起きているかのようですね)は、日本においては仏教と神道が両立する独特の文化があるからです。考え方次第では亡くなるとなぜか倍の人生が始まるとなると、これはこれで面白くて深刻さが和らいだりします。
深刻さが和らぐという点でもう一つ述べると、ピクサー映画「リメンバーミー」の舞台となったメキシコの生死観というのも非常に興味深いです。これはまさに日本のお盆の考え方と同じで、死者の日(こどもの日と大人の日がそれぞれ1日ずつ、あとペットの日とかいうお茶目なものもあった気が…)に先祖がマリーゴールドの橋を渡って帰ってきます。心が揺さぶられるように美しい情景ですね。
死は先祖の暮らす新たな地への旅立ちだから、死を迎える者も送り出す者も、盛大に明るく振る舞うそうです。それは決して死の恐怖から目を背けるためのカモフラージュでは無く、死を受け入れた上での祝福への昇華であり、とてつもなく成熟した精神性が伺えます。私が最も敬意を示す生死観です。
もちろん、身体機能が低下していく実態と、新たな旅立ちという思想とには大きなギャップと葛藤とが現実問題として存在すると思いますが、どう乗りこなして祝福という境地に着地するのか、メキシコ文化に大いに学びたいところです。
試しに家の机にカラベラ(お花柄のお洒落な骸骨)とオフレンダ(自分だけの小さな祭壇)を用意して、この哲学を学ぼうかと考えいます。ファッション性の高いカラベラはAmazonでたくさん売ってますが、オフレンダはマニアックすぎるのか種類少なくピンとくるデザインがありません…
話を元に戻して、一方の唯物論的な思想は現代西洋に多く見られ、死は自然であり無であるという実証主義的/論理的で冷静な思想です。ストア哲学の一部にも見られる考え方で、一見冷徹に感じられるかもしれませんが、これはこれで「生死をみだりに神秘化しない」という、とても洗練された考え方とも言えます。あるがままを受け入れるのが自然という、温故知新というか、原点にして頂点とも言える思想と思います。北欧でも「ヒュッゲ」の精神によく見られます。
同様に、中国の荘子をはじめとする古代の道家思想にも、生も死も自然の一部であり人間が必要以上に介入しないという考え方があるようです。
ここまで死後の世界の有無についてつらつらと書きましたが、改めて、世界中の人々が想いを馳せるのは決して生のみだけでなくその反対の事象もまた然りと知ることができ、恐れとともに何とも言えないロマンを感じます。また、考えれば考えるほどに、恐れが「畏れ」に変わってきている感覚があり、昇華の第一歩を踏み出せているような手応えがあります。
僕は自分の人生を哲学することがとても好きで、変な表現かもしれませんが今の自分の体と精神はこの上ない研究題材です。
目を輝かせてこう語る様を周りは明らかにドン引きしつつも優しく見守ってくれていて、なんだか結局はどうなろうと自分の人生はとても幸せなんだなと実感しています。
僕がこの機会を肯定的に捉えられるのは、自分の影すら掻き消えるほどの太陽が僕の周りをたくさん周回してくれているおかげであり、その光源は僕の数少ない大切な知人たちです。
僕は彼らに何もしてあげられなかったのに、彼らは僕にここまで暖かく優しい心を投げかけてくれる。涙が出るほど嬉しくなってしまいます。
そんなこんなで今日から初回CAPOX治療の入院をしてきます。
ありがとう!をしている会員